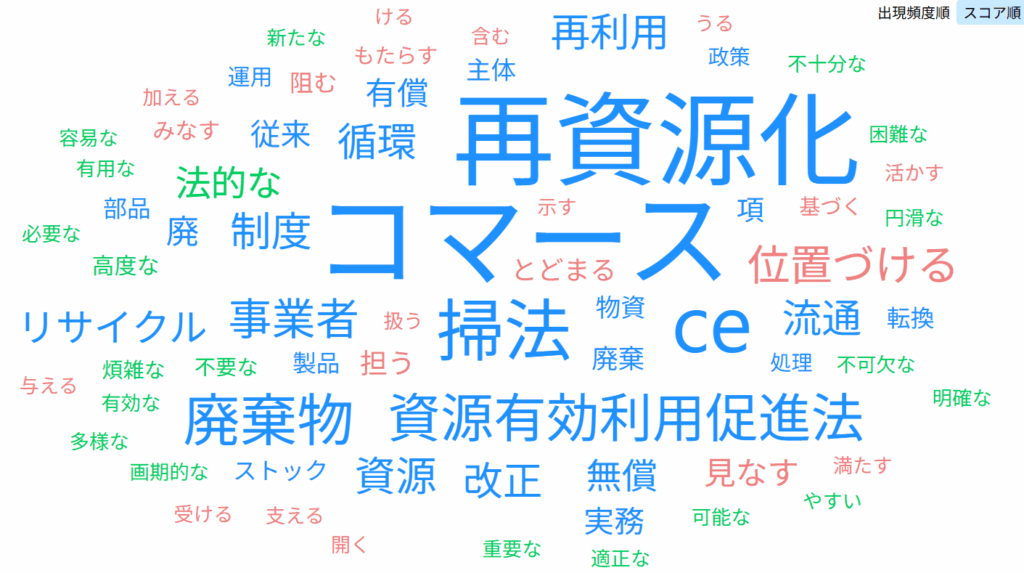改正法文無き「CEコマース」に秘められた「有償無償の壁」の突破 --資源有効利用促進法改正の真に意図するものは--
第0章 はじめに: 見えない改正点
2025年の資源有効利用促進法改正は、一見すると、脱炭素の文脈に関連する条文の修正を除き、制度全体に大きな変更を加えたものではない。しかしながら、経済産業省の公式文書や国会答弁においては、改正文には明記されていない「CEコマースの促進」が強く打ち出され、「シェアリング等のCEコマース事業者の類型を新たに位置づけ、当該事業者に対し資源の有効利用等の観点から満たすべき基準を設定する」と明言された。このような制度の輪郭と文言の乖離は、法改正そのものではなく、改正を機とした既存法解釈の転換に他ならない。
まさにこれは、日本型の行政運用の妙であり、形式的な法文の改定を伴わずして、その制度運用の深度を一段階引き上げる実務的な手法といえる。その中心にあるのが、第2条第4項および第5項に記された「廃棄物ではないが有用である物資」の存在を制度上認知する規定である。この文言は従来から法文上存在していたが、長らくその制度的担い手が曖昧なままに置かれていた。今回、経産省が打ち出した「CEコマース事業者」という概念は、その不在であった主体像を具体化することで、この有用物の流通と活用を制度の中に組み込もうとする試みである。
これは、従来の「廃棄物処理」を出発点としたリサイクル政策の文脈を大きく転換させる可能性を秘めている。すなわち、物資を「廃棄物」として捉えるのではなく、社会の中で使われずに滞留している「ストック」を、再び資源として活かし、必要なところに届けていくという循環経済の新たな相に接続する動きである。
本稿では、この「文言なき改革」が意味するものを、制度的、歴史的、政策的観点から分析し、日本におけるリサイクル・資源循環の転換点を読み解いていく。
第1章 背景: リサイクルからCEストック共有へ
20世紀末以降、我が国のリサイクル政策は、「廃棄物の適正処理」から発展した再資源化の推進に主眼を置いてきた。特に2000年代初頭に整備された循環型社会形成推進基本法をはじめ、各種リサイクル個別法は、製品の最終段階における資源回収と廃棄物量の削減を政策目的として位置づけていた。この枠組みにおいて、資源循環は「廃棄物」としての属性を前提とした処理体系に組み込まれており、リサイクルはあくまで「廃棄の代替手段」として制度設計されていたのである。
しかしながら、サーキュラーエコノミー(Circular Economy, CE)という新たな視座が欧州を中心に台頭してきた近年、こうした枠組みでは不十分であるという認識が広がりつつある。CEは、資源を「廃棄されるもの」としてではなく「社会のストック(蓄積資源)」として捉え直し、これをいかに効率的かつ持続的に社会全体で共有し、回していくかを問う経済思想である。この観点に立てば、従来の廃棄物処理を前提とする再資源化モデルは、その一部に過ぎない。
このような発想転換の必要性が顕在化する背景には、以下のような複合的課題がある:
- 材料レベルのリサイクルではなく、製品・部品・サービスの形での再利用が温室効果ガス排出量や資源消費量の削減により効果的であるとの国際的な研究知見
- 高度経済成長期に蓄積された耐久消費財や建築資材等が都市鉱山化しつつある現実
- コロナ禍や国際紛争によるサプライチェーンの断絶を通じて、国内ストックの活用が地政学的にも戦略性を帯びてきた事実
このような状況において、CE的な循環を支えるには「誰が」「どのように」「何を」循環させるのかという仕組みの再構築が不可欠である。そしてその中核をなすのが「CEコマース(Circular Economy Commerce)」という概念であり、それを支える制度的基盤として、2025年に改正された資源有効利用促進法が新たな一歩を踏み出したのである。
本稿では、リサイクルの概念がCEストックの共有・循環という次元に昇華されていく過程において、制度的に立ちはだかっていた2つの主要な障壁――すなわち「廃掃法の壁」と「有償・無償の壁」――を中心に論点を整理する。そのうえで、近年の法改正、特に「再資源化高度化法」と「CEコマース事業者制度」の創設が、これらの壁をどのように突破し、新たな可能性をもたらしたのかを検証し、将来の制度展開と社会的実装に向けた提言を試みるものである。
第2章 リサイクルを縛っていた制度的障壁
CE型の資源循環を阻んできた制度的障壁は、大きく二つに分けられる。
2-1. 第一の壁:「廃掃法の壁」
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(いわゆる廃掃法)は、廃棄物の適正な処理と公衆衛生の維持を目的としており、廃棄物の収集・運搬・処分を原則として自治体または許可事業者に限定する枠組みを構築してきた。これは高度成長期のごみ処理対策として極めて有効に機能したが、CEの観点からは深刻な制約となっている。
具体的には、製品が一度「不要物」とみなされ、なおかつ譲渡や再販売に至らず無償で提供される場合、それは容易に「廃棄物」と認定されてしまう。この場合、回収・運搬に廃掃法上の許可が必要となるため、リユース・修理・再流通を担う事業者が法的リスクを避けるために取り扱いを断念することが生じていた。
また、たとえ製品が市場価値を持っていても、「使用済み」「使用目的が不明」などの理由で廃棄物扱いされる余地が存在するため、制度的な不確実性が循環経済型ビジネスの拡大を妨げてきた。
この法的リスクの問題は、いわゆるリユース・リペア事業者のみならず、従来のリサイクル事業者や製品の製造・流通に関与する供給側の産業にも大きな影響を与えてきた。リサイクル業においては、使用済製品を再資源化する過程で、再利用可能な部品や素材を回収する場合であっても、それが「無償提供された廃棄物」と見なされれば、直ちに廃掃法の規制対象となる。これにより、リサイクル対象の回収や保管、運搬に対して不要な行政負担が生じるとともに、事業の柔軟性が著しく損なわれる結果となっていた。
また、製造・流通の側から見ても、売れ残り製品や、使用前に返品された商品、あるいは新古品などを市場に再投入しようとする際に、それが「無償譲渡」や「社会貢献目的の提供」とされることで、廃棄物と誤認されるリスクを常に内包していた。その結果として、価値ある在庫や未使用品が「廃棄物」とされ、処理費用をかけて廃棄されるという本末転倒な事例も少なくなかった。
こうした「廃棄物」認定の過剰な裁量は、本来、資源としての寿命を延ばす可能性をもった多様な物資の流通経路を閉ざしてきたのであり、単なる法解釈の問題を超えて、資源循環社会の形成に対する構造的障害として認識されるべきものであった。
2-2. 第二の壁:「有償・無償の壁」
もう一つの制度的障壁は、「有償か無償か」という取引形態が法的属性の判断に強く影響するという点である。
廃掃法の法解釈において、無償での譲渡は「処分の意思あり」とされやすく、すなわち廃棄物としての属性を付与されやすい。これに対し、有償取引は「商品」とみなされ、通常の流通と扱われる。この裁量的な判断構造のもとで、多くの非営利的な活動――たとえば地域住民同士の不要品の譲渡、非営利団体による福祉的リユース活動など――が、法的グレーゾーンに置かれてきた。
これにより、結果的に「循環する社会の価値」が金銭取引の有無に過度に依存するという歪な構図が形成され、価値があるモノでも「無償であるがゆえに処理困難」となる事態が各所で発生していた。
2-3. 業種ごとの具体的制約と問題点
この「有償/無償の壁」によってもたらされる実務上の影響は、自治体やNPO、リユース事業者にとどまらず、リサイクル事業者や製造メーカーにも及んでおり、制度全体としての資源循環の非効率性を生み出してきた。以下に、その具体的な影響を事業主体別に整理する。
| 事業主体 | 有償/無償の壁による主な影響 |
| 自治体 | 家庭からの「無償」排出物が「廃棄物」として処理対象となり、他主体による回収・再利用が困難に |
| NPO・地域団体 | 寄贈物資の無償譲渡が「廃棄物」とみなされることで、保管・運搬・活用に法的制約が生じる |
| リユース事業者 | 回収品が「廃棄物」扱いとなるリスクから、対象品目の選定に消極的にならざるを得ない |
| リサイクル事業者 | 本来再資源化可能な物資も、無償で引き取れば「廃棄物」とされる可能性があるため、収集・運搬の自由度が限定される |
| 製造メーカー | 自社からの発生物を「廃棄物」とせず再利用させるには、形式的な「有償」化が必要となり、逆に再利用の質や自由度を下げる結果となる |
| 家電修理業 | 回収運搬に許可が必要なため、修理拠点への回収を断念し、依頼者が自力持ち込みを強いられる |
| 建設副産物活用 | 建設現場での残材の譲渡が「廃棄物」と認定されやすく、木材端材などの再活用が進まず、焼却・埋立へ回されるケースが多発 |
| 福祉リユース | 非営利の再利用活動が「処分」と解釈され、福祉施設でのリユース提供に法的懸念、活動規模の縮小 |
| 地域資源循環 | 地域イベント等での無償物品流通が規制対象になる可能性があり、バザーやリユース市が縮小または廃止、資源活用の場の喪失 |
特に製造メーカーにおいては、廃棄物と見なされることを回避するため、再販売やリユース品の「有償提供」形式が選ばれる傾向が強い。このような形式的な有償化は、制度的には廃棄物規制を免れる一手段ではあるが、実務上は再利用に対する制約や、品質担保の困難さ、流通の煩雑化を招き、結果として再利用の質や価値を損なう一因となっている。
リサイクル事業者においても、同様の理由から、無償譲渡での回収は法的リスクを伴うため忌避されやすく、再資源化の入口となる収集過程において多くの障壁が立ちはだかってきた。こうした制度的なボトルネックは、現実の資源循環の実装において「廃棄物としてではなく、資源として流通させる」という本質的な目標の実現を、事実上困難にしてきたのである。
2-4. 構造的問題としての共通性
これら二つの壁は、いずれも「モノの価値の社会的定義」と「流通主体の制度的位置づけ」に関わる問題である。廃掃法はモノを「廃棄物」か否かで一律に処理し、有償無償の判断軸も「処分意思」というあいまいな概念に依拠していた。こうした制度設計のもとでは、ストック型循環を担う中間事業者――すなわちCEコマース事業者――が制度的に位置づけられる余地がなく、結果として廃棄処理を経ない「再流通」の仕組みは制度外の活動として扱われることになっていた。
このような構造的な排除が、制度の更新なしにはCEの本質に迫ることができない最大の障壁であった。次章では、こうした障壁の一端を崩す契機となった「再資源化高度化法」による廃掃法の特例措置について検討する。
第3章 再資源化高度化法による「廃掃法の壁」突破の契機
2023年に制定された「再資源化高度化法(脱炭素社会の形成に資する再資源化等の促進に関する法律)」は、これまでの廃掃法による制限の一部を構造的に緩和することを目的としたものであり、サーキュラーエコノミー推進の制度基盤として極めて重要な契機となりうるものである。
この法制度は、脱炭素社会の実現に貢献する「再資源化等行為」に着目し、それを実施する事業者を「再資源化等促進事業者」として指定できる仕組みを導入した。この指定を受けた事業者については、廃掃法における処理責任主体の原則からの特例が認められ、廃棄物の取り扱いに関して一定の柔軟性が与えられる。
すなわち、従来であれば「廃棄物」と見なされる可能性が高かった使用済み製品や副産物についても、その活用が明示的に再資源化等行為として認定されれば、「廃棄物処理」としての処理義務から一定の範囲で除外される。これは、これまでの法体系のなかではほとんど見られなかった大胆な枠組みであり、リユース・リビルド・アップサイクルなど多様な循環ビジネスへの制度的道筋を示すものとなった。
3-1. 制度的意義と実務的効果
この特例措置は、CEを担う事業者にとって以下のような実務的な恩恵をもたらす:
- 廃棄物処理事業者でなくとも、再資源化を目的とする回収・保管・加工が可能になるケースの拡大
- 製品の修理・再組立・パーツ交換などのプロセスにおける「廃棄物」扱いの回避
- 複数の企業・地域間での資源循環ネットワーク構築の法的安定性の確保
また、これらの制度整備により、社会的意義のある中間処理・再資源化プロジェクトがこの法に基づく認定を受ければ「違法処理」と疑われることなく実施可能となり、行政・市民・企業間の信頼関係の構築にも寄与する。
3-2. 関連論考との接続
本章の内容については、本webサイトの「CE論議」で「再資源化高度化法について、特に廃掃法の特例とリユース推進の視点から」(2025年3月、https://circular-inductries.net)においても詳述しているが、そこで論じたポイントを簡潔に要約すると次の通りである:
- 法制度の分断的運用(廃掃法/資源法)から、包括的・戦略的な資源マネジメント法制への統合的転換の必要性
- 再資源化高度化法は、個別法的制度の“隙間”を制度的に埋める調整弁的役割を担っていること
- 「環境政策」から「資源政策」への文脈転換を示唆するものであるという点
このように、再資源化高度化法は単なるテクニカルな例外規定ではなく、むしろ日本におけるCE制度構築の起点とも言える性格を持っており、次章で取り上げる「CEコマース事業者制度」との連携においてその意義はさらに深化する。
3-3. 業種ごとに開かれた新たな可能性
この「再資源化高度化法」による特例措置は、従来、廃棄物処理法の下で制約を受けていた多くの業種にとって、資源循環の実務を根本的に転換する契機となりうるものである。とりわけ「廃棄物該当性」からの脱却を制度的に可能とした意義は大きく、CE型のストック経済への移行に道を開く制度的突破口として、以下のような広範な事業主体に影響を及ぼしうる。
| 事業主体 | 従来の制約 | 特例措置による変化・可能性 |
| リユース・リペア事業者 | 「無償譲渡=廃棄物」扱いとなることから、回収・運搬に廃掃法許可が必要となり、事業拡大に支障 | 「廃棄物ではない」物資の再使用が可能となることで、法的リスクを回避しつつ流通が可能に |
| リサイクル業 | 引取時点での「廃棄物認定」により、収集・運搬の自由が制限される | 排出者が「廃棄物」とせず排出することで、廃掃法に縛られずに再資源化ルートの構築が可能となる |
| 日用品製造業 | 製造過程での規格外品や返品品が廃棄物とされ、有償化による再利用対応を強いられていた | CE的発想での再製品化や部品供給が、制度的に整合しやすくなり、再活用が正面から制度内に位置づく |
| 量販店・小売業 | 不用在庫や回収品を廃棄物として処理せざるを得ず、再販売や寄贈に行政上の壁 | 不要在庫・回収品を「有価物」や「資源」として再流通させる選択肢が拡大 |
| 自動車関連産業 | 使用済部品の再利用が廃掃法の規制を受け、制度上の不安定さがネックとなっていた | 使用済み部品や素材を「廃棄物ではない不要物」として制度的に再使用可能な位置づけに変化 |
| 自治体 | 市民が無償排出した物資が一律「廃棄物」となることで、外部主体による再利用との連携が困難 | 一部物資の「資源的排出」認定を許容することで、地域循環ネットワーク形成に柔軟性が生まれる |
このように、特例措置がもたらす法的な「解放」は、単なる制度の技術的調整にとどまらず、各業種が持つ潜在的な再利用・再資源化能力を社会的・制度的に顕在化させる契機となるものである。特にリサイクル業や量販店、日用品製造業などは、これまで「廃棄物」の裁量的判断により価値あるモノの循環を断念していた歴史を持つだけに、この特例による柔軟な解釈は、現場の循環実務に現実的な恩恵を与えるものである。加えて、地域における自治体の役割も、単なる回収主体から「資源の中継・再分配の構築主体」へと転換する契機となりうる。こうした制度的環境整備は、まさにCE経済への移行を制度面から支える根幹となりうる。
3-4. 「StoR(Stock to Resource)」実現への論点
StoR(Stock to Resource)は、東北大学の中村崇名誉教授らによって提唱された概念で、都市鉱山や使用済製品など、社会に蓄積された「ストック(埋蔵資源)」を「資源(リソース)」として再活用する枠組みを指す。特に金属資源のリサイクルを対象とし、地上資源の計量的把握と動的管理を重視する点に特徴がある。このStoRの考え方は、さらに、金属資源に限らず、製品・部品・装置など社会全体に眠る「活用可能な未使用資産」にまで拡張され、CE(サーキュラー・エコノミー)全体のストック循環の中核概念として再定義することができる。すなわち、StoRは、リサイクル中心の「出口」戦略から、再利用・再流通を含む「入口と中間流通」に焦点を当てるCE型資源管理の理論的基盤となっている。
このStoRの鍵となるのは、社会に既に存在するストック(製品・部品・副産物等)を「廃棄物ではなく価値あるリソース」として正当に扱える法制度の存在である。再資源化高度化法は、まさにこの「認定基準の設置」と「処理義務の緩和」を通じて、価値の再定義を制度的に可能とした。これにより、流通のプロセスそのものが再設計され、持続可能なストック共有のための商取引=CEコマースの成立条件が整い始めたと言える。
次章では、この動きがさらに発展し、「廃棄物ではない不要物」という新たな制度的カテゴリと、それを担う制度主体としての「CEコマース事業者」の創設へとつながった経緯と意義について論じる。
第4章 資源有効利用促進法の改正に含まれた有償無償の壁の突破
2025年の資源有効利用促進法の改正を巡る報道や政策資料のなかで、経済産業省が「CEコマース」を前面に押し出して説明している点は注目に値する。しかし実際に公布された法文上には、「CEコマース」や「CEコマース事業者」といった文言そのものは明記されていない。にもかかわらず、政策資料上で「シェアリング等のCEコマース事業者の類型を新たに位置づけ、当該事業者に対し資源の有効利用等の観点から満たすべき基準を設定する」とされたことは、逆に本改正がこれまで制度的に立ち入り難かった領域、すなわち「有償無償の壁」の突破に踏み込む契機として意図された可能性が高いことを示している。
この観点から重要なのは、今回の法改正それ自体に新たな規定が加えられたというよりも、「CEコマース」的な制度運用を可能とするための、既存条文の再解釈と制度運用の枠組み変更が行われた点にある。特に、第2条第4項および第5項の存在は従来から指摘されていたにもかかわらず、その制度的可能性が十分に引き出されてこなかったという経緯がある。
4-1. 第2条第4項・第5項の再評価
改正前から存在した以下の条文に改めて光を当てたい:
(第2条第4項)この法律において「再資源化」とは、製品その他の物が廃棄されることなく、再生資源又は再生部品として利用されることをいう。
(第2条第5項)この法律において「再資源化製品」とは、再資源化に係る製品その他の物であって、主務大臣が指定するものをいう。
これらの条文は、表面上は再資源化の対象とする物の定義にとどまるが、「廃棄されることなく」という表現が含まれることにより、「廃棄物ではないが利用されていない物」すなわち、在庫・返品・余剰・使用されなかった製品などを制度的に包含し得る可能性を秘めている。
CEコマース事業者制度は、この既存条文のもとで運用可能な形で、「再資源化製品」の回収・再利用を行う主体を、認定制度を通じて制度化しようとするものであると理解するのが妥当である。
4-2. 公布法文になき「CEコマース」制度の実質的展開
CEコマースの促進は、現行公布法令には明記されていない。しかしながら、経産省の説明文書、国会答弁、政策ロードマップでは、明確にその推進が宣言されており、事実上の行政解釈により制度展開されようとしている点が重要である。
この構造は、日本の法制度における「省令・運用通知・告示」を通じた解釈的法運用の典型であり、制度的正統性は担保されつつも、その実効性と継続性には今後の運用実績が問われることとなる。
4-3. 制度運用が鍵を握るCE型R&Sへの転換
「この法改正があったから変わる」のではなく、「この法改正を機に、制度運用を通じてCEコマース事業者制度を確立し、運用していくことでR&S事業の形態がCE型に進化する」という方向性が、今回の真の趣旨である。
すなわち、制度文言に依存するのではなく、制度のもつ潜在的包摂力と、その解釈・運用の設計が実質的な社会変革を可能にする。今回の改正は、その可能性を政策的に開示し、制度的にそれを支える構造を形成したという点で、CE型経済の時代における画期的なターニングポイントと位置付けるべきである。
次章では、こうした構造のもとで創設された「CEコマース事業者」認定制度の法的位置づけと、旧制度からの進化の具体的内容について論じる。
第5章 CEコマース事業者制度の法的位置づけと前法からの進化
今回の改正法において、「CEコマース事業者」という新たな認定制度が導入されたことは、制度的な空白を埋める画期的なものであったが、その萌芽は旧法の条文にも見て取れる。
旧資源有効利用促進法の第2条第2項には、以下のような定義が存在していた:
(旧法 第2条第2項 抜粋) この法律において「再資源化」とは、製品その他の物が廃棄されることなく、再生資源又は再生部品として利用されることをいう。
この条文においても、対象が「廃棄されることなく」と明記されており、すなわち「廃棄物」以前の段階にある不要物(未使用品、返品、余剰在庫等)も含意されていたことは明らかである。
しかしながら、当時はこれらのモノを再流通の対象として扱う制度的主体が存在せず、また「有償か無償か」によって取扱いの法的位置づけが揺らぐ構造が解消されていなかった。そのため、非営利的な寄贈型の再使用活動が「無償→廃棄物」と見なされ、リスク回避的に事業化が阻まれるという事例も多く発生していた。
5-1. 改正前後の法運用の違い(比較表)
| 項目 | 旧資源有効利用促進法 | 2025年改正後の期待される法運用 |
| 対象物の範囲 | 再生資源・再生部品(廃棄物を前提) | 廃棄物以外の不要物も対象に明確化 |
| 主体の定義 | 特定事業者のみ(義務ベース) | CEコマース事業者の認定制度を新設 |
| 有償/無償の扱い | 明確な制度的考慮なし | 有償無償を問わず「ストックの流通」を前提とした制度運用 |
| 活動の自由度 | 廃棄物処理法との整合で制限 | ストック活用型リユース/シェアリングに法的裏付け |
5-2. 制度進化の意義
このように、旧法においても制度理念としては「廃棄前の再利用」を含意していたが、それを担う主体が制度上位置づけられていなかった。これに対して、今回の改正では「CEコマース事業者」の定義とともに、廃棄物ではないが活用されていないモノを制度的に扱えるようになった点に大きな意義がある。
また、経済産業省の説明文書等においても、以下のような文言が明記されている:
「シェアリング等のCEコマース事業者の類型を新たに位置づけ、当該事業者に対し資源の有効利用等の観点から満たすべき基準を設定」
このように、改正法のもとでの制度化により、制度上の壁であった「廃棄物でなければ制度外」という従来の矛盾が解消されつつある。
次章では、こうした制度整備を受け、どのような産業・業態が今後CEコマースの担い手となりうるかを具体的に示していく。
第6章 制度変革によって開かれる各産業の可能性と新たな担い手
資源有効利用促進法の改正を契機として、さまざまな産業が従来制度下で直面していた障害を超え、新たな事業展開の可能性を持つこととなった。本章では、CEコマース事業者制度を受けて、産業ごとにこれまでの障害とその克服後に広がる可能性を具体的に述べる。
6-1. 各産業における制度的障害と展望
| 産業分野 | これまでの主な障害 | 今後の可能性 |
| リサイクル業 | 無償提供された物品は廃棄物とみなされ、許可や届出が煩雑。法的リスクのため回避傾向。 | CEコマース事業者としての認定により、無償品を制度下で合法的に流通・再資源化できる。 |
| 家庭用品販売業 | 回収品は廃掃法の枠に入り、業として再販売・再利用できず、製造業者に一任。 | 使用されなかった製品や返品を「不要物」としてCE流通に乗せることが可能に。 |
| 建設業・住宅設備業 | 解体後の資材は産廃扱いとなり、再利用を阻む障壁に。 | 副産物の再資源化や部品単位での再使用が制度的に支援される。 |
| 地域コミュニティ(非営利含む) | 寄付品・回収物の取扱いが無償のため廃棄物と見なされやすく、制度的に不安定。 | 地域循環の担い手としてCE事業者登録により合法的な交換・分配が可能に。 |
| リース・シェアリング業 | リース後の残置品や破損品の再処理が法的グレーゾーン。 | 保守後の再販売・分配がCE制度により明確化され、再投入が容易に。 |
6-2. レアメタル循環と「StoR」の視点
CEコマースの制度化は、特にレアメタルのように希少かつ循環の必要性が高い資源の再活用においても重要な布石となる。これまでの制度では、廃棄物処理法に基づき処理された使用済製品からのレアメタル回収は、コストや規制面で困難が伴った。
たとえば:
- 小型家電中の金・パラジウムなどの希少金属を回収・再資源化する過程では、従来、廃棄物処理法に基づく許可業者が、収集運搬・選別・破砕・精錬といった高度に分業化されたプロセスを担ってきた。これらの業者の技術とインフラは、資源循環の中核を成す不可欠な基盤であることに変わりはない。一方で、CEコマース事業者制度の運用により、製造業者やリユース事業者が「廃棄物ではない不要物」としての段階で直接回収・分別に関与できるようになれば、収集・選別の初期段階において、再資源化の質を高めたうえで、精錬やリサイクル業者とより的確に連携できる体制が構築可能となる。小型家電中の金・パラジウムなどの回収には、許可業者による収集運搬・選別・破砕・精錬のプロセスが必要だったが、CE事業者が直接引取り・再資源化に関与できる余地が生まれた。これにより、資源循環全体の質が向上すると同時に、専門性の高い処理業者にとっても、より安定した高付加価値処理を行う機会が拡大する
- 特にリサイクル事業者にとっては、工場や物流拠点から排出される「規格外品」「工程発生くず」「返品製品」などの扱いが大きく変わる。これまで「廃棄物」として処理しなければならなかったこれらの資源が、CEコマース制度の運用により「廃棄物でない不要物」として再販売・再加工・部品供給に回せる制度的基盤が整えば、廃掃法による規制回避だけでなく、新たな取引市場の創出による事業機会拡大にもつながる。
- EVバッテリーに関しても、解体後のセルやモジュールの再利用が、明確な制度的位置づけのもとで迅速に行えるようになりつつあり、ストック品の「再流通」プロセスが加速している。従来のような「一律廃棄」処理ではなく、価値評価に基づく分別と再活用が制度的に可能となれば、再資源化の質的向上と収益性向上の両立が見込める。
- 自動車製造業などの大規模発生者にとっても、製造工程から日々排出される大量の副産物や規格外部品は、従来「利材化」として、いわば廃棄物としての性格を前提に処理され、その目的は主として廃棄物量の削減に置かれていた。しかし、CEコマースの制度的運用により、これらの物資が「廃棄物ではない不要物」として明確に位置づけられ、適切な技術基準や流通基準のもとで信頼性の高いリサイクル事業者と連携して再流通・再利用が図られるようになれば、単なる減量ではなく、資源価値そのものを活かす方向へ転換が可能となる。その結果、廃棄物処理に伴うコストの削減にとどまらず、再資源化物の売却による収益化、さらには環境配慮型の調達体制を整備することでのESG評価の向上など、企業にとって多面的かつ戦略的な経済的メリットを享受できる。これは、利材化を起点とした廃棄物管理から、CE型の資源戦略への転換を示す重要な一歩である。
このように、CEコマースの枠組みは、まさにStock to Resource(StoR)の理念に基づき、「ストックされた資源を再び資源として活用する」ことを制度的に支えるものであり、単なるリサイクルを超えた高度な循環経済の担保となる。
次章では、これら制度と実務の整合を実現する上で必要な基盤整備と、将来的な拡張可能性について検討する。
第7章 実務との整合と制度拡張のための基盤整備
CEコマース事業者制度が制度上準備されたとはいえ、実務との整合性を高め、制度が円滑に運用されるためには、いくつかの基盤整備が不可欠である。
第一に、現場のリユース・リサイクル活動と行政側の制度理解との間には、未だ大きな乖離がある。CEコマース事業者認定制度の趣旨を地域自治体や関連業界団体に明確に伝達し、地域の運用マニュアルや審査基準の整備を進める必要がある。
第二に、廃棄物処理法・家電リサイクル法・資源有効利用促進法の各制度間における「横断的整合性」を確保する制度的整理も急務である。たとえば、廃棄物と不要物の線引きが現場で曖昧になった場合の対応、あるいはCEコマース事業者の認定と既存の再資源化業者との責任分担・流通の明確化が求められる。特に、既存の再資源化事業者がCEコマース事業者として認められる要件の整備は重要である。
第三に、CEプラットフォームとして機能する流通・追跡・品質保証のデジタル基盤の整備も重要である。マイナンバー制度や環境省の電子マニフェスト制度のような仕組みと連携し、製品・部品単位でのライフサイクルデータの記録・管理・連携を支援する技術基盤の導入が必要となる。
さらに、自治体や中小事業者が参画しやすい形での補助制度や税制支援、国による先進モデル事業の支援展開など、政策的誘導も併せて検討すべきである。
第8章 サーキュラーエコノミー社会への制度的転換と今後の展望
本稿で一貫して主張してきたように、リサイクルを単なる「廃棄物処理の一工程」から、社会全体で「ストックされた資源を有効に循環させる仕組み」へと脱皮させるには、制度的転換が不可欠であった。その意味で、再資源化高度化法と資源有効利用促進法改正の連動は、CE時代の基盤となる大きな第一歩である。
今回の改正により、「廃棄物ではない不要物」の存在が実践的に位置づけられ、その循環を担う主体としての「CEコマース事業者」が制度的に登場したことは、社会経済システム全体における物資のフローからストックへの視点転換を象徴している。
この動きは、エネルギー・資源の脱炭素化、国内循環の促進、廃棄物量の削減など、さまざまなGX政策との親和性を持ち、将来的には国土利用、災害対応、都市設計、教育分野などにも波及し得る構造転換である。
今後は、「モノのサーキュラー・エコノミー」にとどまらず、「情報」「人材」「空間」といった多様な社会ストックを活かす総合的なストック経済への展開が期待される。
そのためには、制度設計の継続的なアップデート、現場との双方向的対話、そしてLCAや資源指標などの可視化指標による価値評価が求められる。
我々は今、廃棄物処理型のリニア経済を脱し、「必要なところに、必要な資源を回す」ストック循環型社会への扉を、ようやく開こうとしている。
参考
成長志向型の資源自律経済の 確立に向けた取組について 令和7年3月 経済産業省 GXグループ 資源循環経済課 https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/iinkai3/economysystem_5/siryo6-2-3.pdf
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000048
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました から 新旧条文対象
(文責: サーキュラーエコノミー・広域マルチバリュー循環研究会 代表 原田)
https://circular-industries.net
/